「サメの食事」と聞くと、どんな光景を思い浮かべるでしょうか?
恐らく多くの人が、歯をむき出しにしたサメがアシカやオットセイに飛び掛かる激しいハンティングや、血の臭いに興奮したサメが暴れ回る狂乱錯餌のようなものを想像すると思います。
しかし、これから紹介する内容を知ると、そのイメージが変わるかもしれません。
2025年5月、ハワイの海に浮かぶクジラの死骸を、イタチザメとヨゴレという2種のサメが一緒に食べている様子についてまとめた論文が公開されました。
どちらも危険で凶暴なサメとして認識している人が多いと思いますが、現地で撮影された映像には、サメたちが争うことなくクジラの死骸を食べる様子や、彼らなりの秩序や社会性を感じさせる行動も収められていました。
- 具体的にどんな行動が見られたのか?
- 今回の行動から何が言えるのか?
- サメがクジラを食べることにどんな意味があるのか?
今回は、クジラの死骸を一緒に食べるサメ達について解説をしていきます!
解説動画:危険なサメが仲良く食事?クジラというご馳走を前にしたサメたちの意外な行動とは?【イタチザメ】【ヨゴレ】
このブログの内容は以下の動画でも解説しています!
※動画公開日は2025年7月1日です。
イタチザメとヨゴレについて
今回の研究で登場するのは、イタチザメとヨゴレというサメです。一応どんなサメたちか簡単に紹介します。
イタチザメ(Galeocerdo cuvie)

イタチザメはメジロザメ目イタチザメ科イタチザメ属に分類されるサメです。
大きさは全長約2.2~3.5m、大きいものでは5.5mにも達します。
頭が大きくて吻が丸みを帯びており、背中側に独特の縞模様を持つなどの特徴で見分けることができます。
イタチザメは沿岸域や島の周りなどに主に分布するサメで、水深の浅い場所にも現れることがあります。
ヨゴレ(Carcharhinus longimanus)

もう一種のサメ、ヨゴレはメジロザメ目・メジロザメ科・メジロザメ属の仲間です。
大きさはイタチザメよりもやや小ぶりで、1.7~2.2mほど。3mを超える記録もあるようですが、かなり稀だと思います。
ヨゴレも模様が特徴的なサメで、第一背鰭、胸鰭、腹鰭、尾鰭の先が白く、第二背鰭や臀鰭の先は黒くなっています。この模様がヨゴレっぽいというのが名前の由来です。
ヨゴレは外洋性のサメで、基本的にはかなり沖の方を泳いで暮らしています。
イタチザメはまだしも、ヨゴレはなかなか観察する機会がないため、今回の研究はヨゴレの腐肉食を観察できたというだけでも、かなり貴重なものだと言えます。
仲良くクジラの死骸を食べるサメ達
そんな観察機会の少ない貴重なヨゴレと、危険ザメとして悪名高いイタチザメが、仲良くクジラの死骸を食べていたというのが、今回のメインテーマです。
劣化したクジラの死骸に群がるサメ
食事風景が観察されたのは、米国ハワイ州のハワイ島近海です。
2024年4月9日10時30分頃、ハワイ島の西から10kmほどの沖合を航行していた観光船が、酷く劣化したクジラの死骸を発見します。
死骸の大きさは長辺3m×短辺2m×高さ2mほど。観光船の人によれば若いナガスクジラ類だったかもしれないそうですが、「デカい肉と脂肪の塊」と言えるような状態だったため、クジラの種までは特定されていません。
観察が始まった時点で、すでに死骸の近くに2尾のヨゴレが集まっており、死骸を食べ始めていました。
さらに観察から1時間以上経過する頃には、別のヨゴレやイタチザメが姿を見せます。
観光船が観察を終えた19時頃までの間に、少なくとも7尾のヨゴレと5尾のイタチザメが死骸の周りに現れました。
サメ達は以下のような様々な方法でクジラの肉を噛み千切っていきました。
- 深みから垂直にクジラの向かっていき大きく肉を噛み千切る。
- 早い速度で連続して噛み続ける。
- 頭を動かして素早く肉を噛み千切る。
- 深く肉を噛んだ状態で回転する。
秩序と社会性を感じさせる摂餌行動
脂肪をたっぷり含んだクジラ肉というご馳走を前に大型サメ類サメがこれだけ集まれば、肉を奪い合う大混戦が起きそうですが、実態は非常に平和的だったそうです。
研究者はエサの食べ方や食べている個体を識別するために水上と水中それぞれの映像を記録し続けましたが、同種間・異種間いずれにおいても、攻撃的な行動は見られませんでした。
さらに、サメ達が体の大きさに基づくヒエラルキーを持っていると示すような行動が見られました。
2尾のサメが同時に死骸に近づくと、体の小さなサメが方向転換して大きなサメに譲ったり、逆に小さなサメが食べている時に大きなサメが近づいてくると、小さなサメはすぐに離れていきました。
また、死骸の周りには性別も大きさも様々な個体が集まっていましたが、死骸を直接食べていたのは3~4mほどの大きなイタチザメと、集まっていた中では最大(約2.5m)のヨゴレに限られました。
それ以外のサメ達は水深5m付近に留まり、大きなサメ達が食べる時に落ちてくる肉片や彼らが吐き出されたものを食べていたそうです。
これらの観察記録から、サメ達は自分と他のサメのサイズ差を元にした一定のヒエラルキーを認識しており、それに合った摂餌行動をしていたと推測できます。
サメ達が何故、どのように?ある種の社会性を獲得したのか気になりますが、血の臭いですぐ興奮する凶暴な生き物というイメージを持っていた人は、意外に思えたのではないでしょうか。
サメは常に平和的にクジラを食べるのか?
クジラの死骸を前にしたサメ達が平和的に食事する光景は他でも確認されています。
例えば、南アフリカのフォールス湾では、一つの死骸を7~8尾ほどのホホジロザメが同時に食べている様子が記録されています。
これらの摂餌行動をまとめた研究によれば、クジラを食べるサメたちは時にぶつかったり胸鰭が重なり合うような距離にいたにもかかわらず、攻撃的な行動は見られなかったとのことです。
このホホジロザメの事例でも、大きなサメが脂肪が最も多い部分を優先的に食べ、それより小さなサメは脂肪分の少ない場所を食べ、さらに小さなサメはクジラから距離をとって流れてくる”おこぼれ”をもらうという、体のサイズに基づいた序列が見られました。

さらに、サメ以外にも思わぬ珍客が現れることもあります。
2017年9月豪州の西オーストラリア州の沖で、全長15m近い大きさのザトウクジラの死骸を、イタチザメとイリエワニが一緒に食べている様子が観察されました。
イリエワニは塩類濃度の高い場所への適応能力が高く、海にも現れることがあります。
ドローンで撮影された映像では彼らは互いに争うことなくクジラの肉を食べていました。
実際の映像はコチラ↓
ただし、サメ達が常に平和的にクジラを分け合うというわけではありません。
ニューカレドニアで17.4mのシロナガスクジラの死骸を食べるイタチザメを観察した事例では、攻撃的な行動が見られたそうです。
今回ハワイで観察された死骸はニューカレドニアの時よりも小さかったのに、何故イタチザメが秩序だった摂餌を見せたのか?なぜ場所によって行動が違うのか?
今回の論文では、明確なことは分かっていないとしながらも、以下のような見解が示されています。
It is not clear why TIG exhibit such contrasting social behaviors in different locations, but it could be related to differences in food availability, with sharks being less competitive if resources are abundant and/or variation among individuals and personalities, which may trigger inter- or intra-specific risktaking or risk-averse behaviors.
(何故イタチザメが異なる場所で対照的な社会行動を見せたのか明確には分からないが、資源が豊富であればサメが競争的でなくなるというエサの量の問題か、種間・種内でリスクのある行動をとらせる、あるいは回避させる個体ごとの性格の問題どちらか、あるいは両方が関係しているかもしれない)
『Novel observations of an oceanic whitetip (Carcharhinus longimanus) and tiger shark (Galeocerdo cuvier) scavenging event』より引用(訳は筆者。文中のTIG はイタチザメを示す)
要するに、その海域にエサが豊富にあったからサメたちが争わずに秩序だった摂餌行動を見せた可能性や、リスクをとってでも獲物を独占したがるサメ、無駄な争いを避けるサメなど性格の問題だった可能性もあるというわけです。
「魚は知能が低い」とか「機械的だ」とか思っている人も多いですが、サメ類にも一定の学習能力や社会性があり、餌の好みや人への慣れやすさなどに差が出ることもあります。
あくまで可能性の一つですが、サメの個性による行動の違いというのも、案外あり得るのかもしれません。
サメの腐肉食による生態系への影響
最後に、サメがクジラの死骸を食べることにどんな意味があるのかを考えていきたいと思います。
僕はサメが大きな肉にかぶりついているのを見ると可愛いと感じますが、クジラには良くも悪くも思い入れが強い人が多いので「サメに食べられて可哀相」と思う人もいるかもしれません。
しかし、大型サメ類がクジラを食べることで様々な生物に恩恵がもたらされます。
クジラの腐肉食で恩恵を得る生き物たち
まずは当たり前の話ですが、クジラを食べるサメたち自身が大きな肉の塊を苦労せずに手に入れるというメリットを享受できます。
また大きなサメがクジラを食べると、小さな肉片が飛び散ったり、柔らかくて食べやすい組織が露出したりします。こうした部分は、より小さなサメや他の魚たちの食料になります。
今回の研究でも、大きなイタチザメがまき散らした食べ残しや吐き戻しを小さなサメたちが食べていました。
クジラの死骸により形成される生態系
さらにクジラが深海に沈んでいった場合、「鯨骨生物群集」という非常に興味深い生き物たちの営みが生まれます。
沖合で死亡したクジラが岸の方に流れ去れるケースもありますが、そのまま海底深くに沈んでいった場合、以下のようなプロセスで独自の生態系が形成されます。
筋肉や内臓が残っている状態でクジラが沈めば、カグラザメやコンゴウアナゴなどの動物が集まってきて食べつくします。
そうして骨が露出すると、ホネクイムシなど、骨に含まれる有機物を栄養として利用する生物が現れます。
やがて骨に含まれる有機物を微生物が分解することで硫化水素が発生すると、今度はその硫化水素をを利用して有機物を作る細菌類や、そうした細菌類を体内に住まわせている貝類などが集まってきます。


このように、深海に沈んだクジラの死骸を中心に形成される生物の集まりを「鯨骨生物群集」と呼びます(厳密には骨に含まれる有機物がすべて使われた後に鯨骨が単なる生物の住み家となる「懸濁物食期」というフェーズも存在するとされていますが、確認されていません)。
死んでしまったクジラの死骸は様々な生き物を支える資源となります。そしてサメの腐肉食は、他の生物が利用しやすい状態にするという、重要な役割を果たしているんです。
まとめ
今回は「クジラを仲良く食べるサメ達」というテーマで解説をし、クジラの死骸という獲物を前にしたサメが見せた、ヒエラルキーに基づく秩序だった摂餌行動について紹介してきました。
実際に仲良くしていたのかは分かりませんが、サメの社会性という観点からも興味深い事例だったと思います。
また、クジラという人気な動物の死骸が食べられる様子は人によってはショッキングかもしれませんが、これも生態系において大きな意味のあることだというのは理解して欲しいです。
参考文献
- David A. Ebert, Marc Dando, and Sarah Fowler 『Sharks of the World a Complete Guide』2021年
- JAMSTEC『大西洋で、世界最深の鯨骨生物群集を発見!』2016年
- Molly Scott, Olivia Miller, Devon Stapleton, Kayleigh Grant『Novel observations of an oceanic whitetip (Carcharhinus longimanus) and tiger shark (Galeocerdo cuvier) scavenging event』2025年
初心者向け↓
中級者向け↓


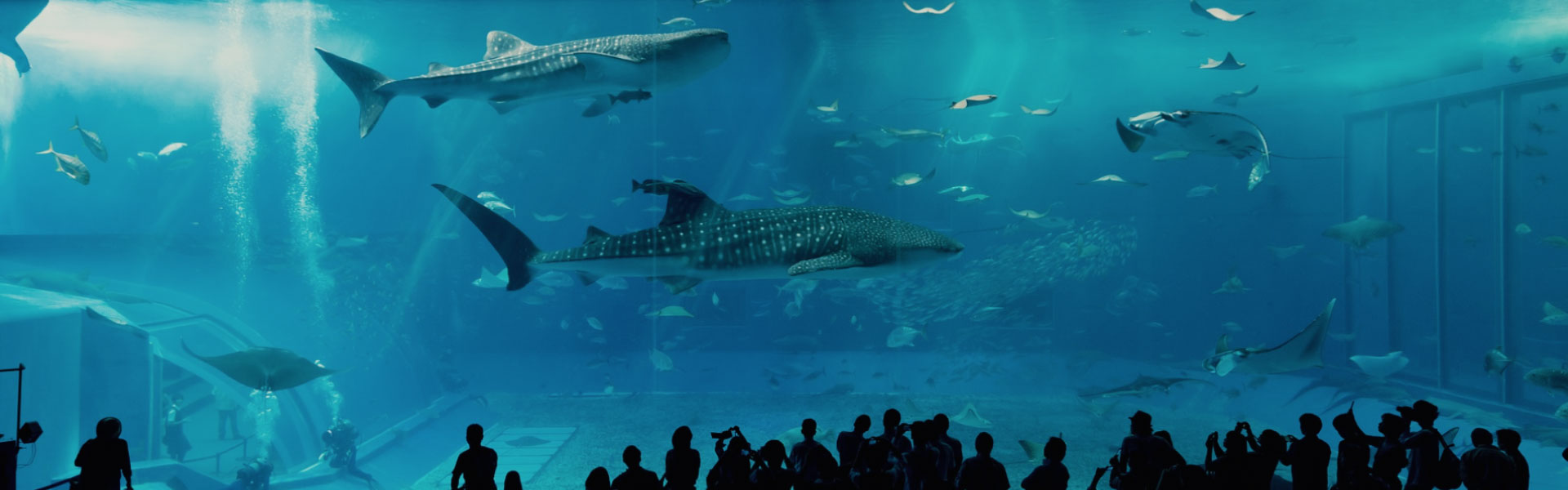
コメント